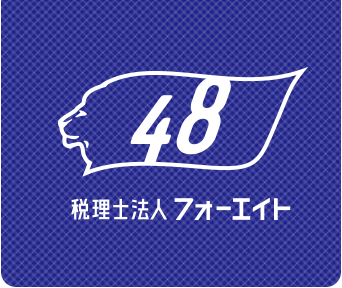

お電話でのお問い合わせ
受付時間(平日)
9:00~20:00
0120-400-800

お問い合わせ
年中無休|24時間受付
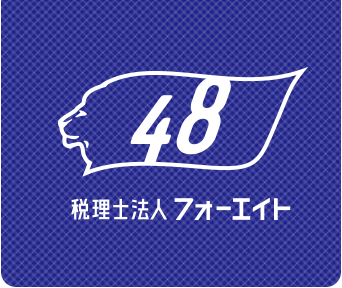

お電話でのお問い合わせ
受付時間(平日)
9:00~20:00
0120-400-800

お問い合わせ
年中無休|24時間受付
2020年7月31日

相続での遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
遺贈を考える際には、これらの違いを理解して、適切な方法を選択することが重要です。
相続における遺贈について、確認しておきましょう。
遺贈とは、遺言によって遺産を贈与することです。
遺贈する場合には遺言書を作成する必要があり、そうすることで本来は相続人となることができない友人などに、財産を譲り渡すことができます。
遺贈において、財産を譲り渡す者を遺贈者、財産を譲り受ける者を受贈者と言います。
この遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2つがあります。
特定遺贈と包括遺贈では、財産の範囲や放棄できる期間などが異なっており、遺贈を考える際には違いを理解しておいた方が良いでしょう。
特定遺贈は、遺産の中から特定の財産を贈与することです。
例えば、”遺産である所在地○○にある土地を内縁の妻に遺贈する”といった内容の場合は、特定遺贈となります。
特定遺贈の対象となる財産は、家や土地などの不動産、現金などの特定できる財産です。
基本的には、マイナスの財産まで受け取る必要はありません。
特定遺贈を放棄するには、放棄の意思表示を遺言執行者にするだけでできます。
どの財産を遺贈するか遺言で決まっているため、それを受け取るかどうかを伝えるだけです。
遺贈を放棄できる期間としては相続の放棄と異なり、被相続人が亡くなった後、いつでも放棄することができます。(民法986条1項)
包括遺贈は、遺産の全体から一定割合が決めてあり、それを贈与することです。
例えば、”全財産から1/8を介護してくれた長男の配偶者に包括して遺贈する”とあれば、包括遺贈となります。
包括遺贈の場合は、包括遺贈者は相続人と同じ義務と権利を持ちます。
包括遺贈の対象となる財産は、遺産の中から割合分を遺贈となるため、全財産が対象です。
その全財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も対象となり、負債や借金などがあった場合にはそれらも遺贈します。
これらをどのように包括遺贈するかは、相続人たちが行う遺産分割協議に参加し、どの財産を受け取るか決めます。
包括遺贈を放棄するには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、裁判所への申述が必要です。
包括遺贈の受遺者は、相続の放棄・承認に関する規定が適用されるので、
3か月以内の申述をしなかった場合には、例外を除いて遺贈の放棄ができなくなってしまいます。
包括遺贈者は通常の相続人と同じように相続の義務と権利を持つため、相続放棄と似た手続きとなります。
特定遺贈や包括遺贈により、法定相続人の相続権などが侵害されることも考えられます。
そのような際にも、相続人には最低限の相続分である遺留分が保証されています。
法定相続人の相続分が、遺言により侵害されていることがわかった場合には、遺留分を請求することができます。
しかし、遺言を残した被相続人の意思を汲んで、相続の権利を主張しないという方法もあるかもしれません。
形見の品などで手元に置いておきたい財産があれば、その分のみを請求することもありでしょう。
遺留分を請求する際には、法定相続人の相続順位を確認しておきましょう。
基本的には、自分より上の相続順位の者がいる場合には、相続することはできません。
また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、その点については注意しておきましょう。
受贈者が遺贈を放棄した後、その子が遺贈したいと申し出てくる場合も考えられますが、指定された受贈者の子が代襲することはできません。
遺贈を放棄された場合は遺言による遺贈は無効となり、その財産は改めて遺産分割協議でどのように相続するか決められます。
受贈者が放棄しても、その子は遺贈することはできず、受贈者が放棄した財産については、他の相続人間による遺産分割協議で決め直すことになるということは覚えておきましょう。
遺贈といっても、特定遺贈と包括遺贈は異なります。
遺言書作成にあたり遺贈を考えている場合には、それぞれの違いを理解してどのように遺贈したいか考えておきましょう。
被相続人の方の意思を尊重した財産分割や、効果的な節税を考慮した遺贈など、幅広くご相談を承っていますので、ぜひ1度ご連絡ください。