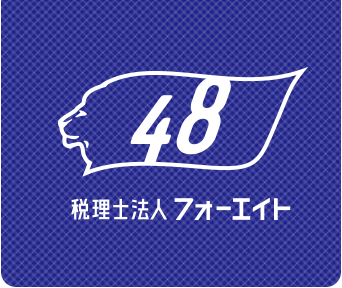

お電話でのお問い合わせ
受付時間(平日)
9:00~20:00
0120-400-800

お問い合わせ
年中無休|24時間受付
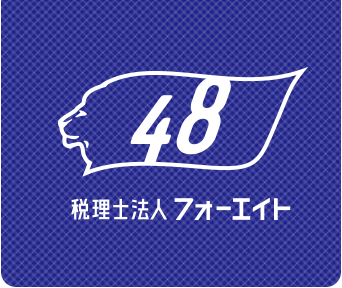

お電話でのお問い合わせ
受付時間(平日)
9:00~20:00
0120-400-800

お問い合わせ
年中無休|24時間受付
2018年7月13日
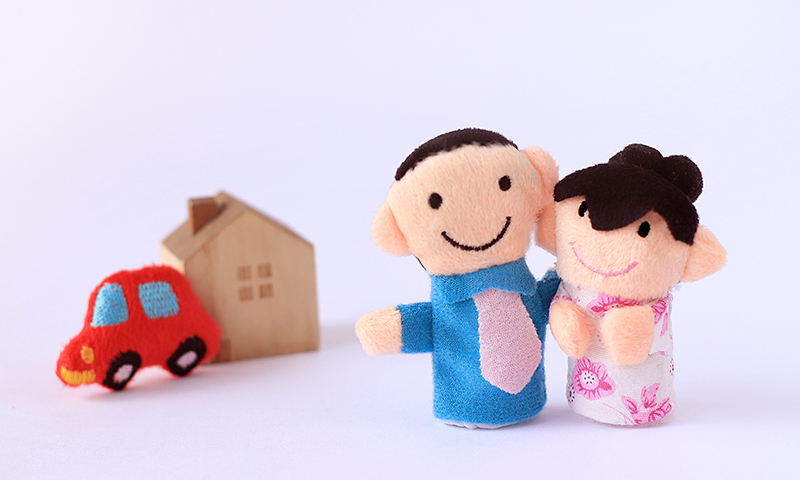
日本の相続における配偶者の優遇は、他の国に比べて不十分な現状があります。
それらの問題が少し改善されるように、民法の改正法案が提出されました。
そして、平成30年7月6日の参議院本会議で与党などの賛成多数で、可決・成立しました。
その中から、配偶者居住権の創設についてご説明します。
これまで配偶者は、相続が発生した際に、相続分の関係から今まで住んできた家を出なければいけなくなったり、家を財産として受け取ることができても現金をほとんど手にすることができなかったりなど、様々な問題がありました。
この問題は、居住権と所有権を分けることで、回避できるものでした。
それらを背景として、配偶者の生活保障を充実させるため、配偶者居住権の創設が審議されました。
今回の民法改正によって、配偶者の居住権を確保して、問題解決に踏み切った形になります。
現在、創設が検討されている配偶者居住権とは、相続が発生した際に、配偶者が被相続人の所有する不動産の居住権を獲得できる権利のことです。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、生前贈与や遺贈、遺産分割協議によって、被相続人とその配偶者の住居を遺産分割の対象から外すことができます。
相続税などの心配をすることなく、住まいや生活資金を保証してくれる制度です。
この配偶者居住権の創設は、短期居住権と長期居住権の2つに分けられます。
それでは、これらの具体的な内容と違いは何でしょうか。
これが、配偶者の生活保障として、1番手厚い配偶者居住権です。
被相続人が亡くなった時に、贈与や遺産分割協議によって取得した居住権により、長期~亡くなるまでそこに住むことができます。
つまり、被相続人の配偶者は、自身が亡くなるまで無償で、被相続人の住居に住むことができます。
この短期居住権は、配偶者の居住権を短期的に保護する方策として設けられています。
被相続人がなくなり相続が発生した時に、被相続人の所有する不動産に配偶者が無償で住んでいた場合に適用される権利です。
配偶者は、遺産分割協議で決定したことが実行されるまでの間(6か月程度が妥当とされている)、無償でその不動産を使用できます。
つまり、残された配偶者は、被相続人が亡くなった後も6か月程度まで、無償で不動産に居住することができます。
短期居住権を取得した後に、長期居住権を取得することもできますが、その場合には短期居住権は消滅します。
これまで問題として考えられてきたものについて、ここでご説明します。
子どものいない夫婦の場合、先祖代々受け継いだ土地や建物などの不動産を、配偶者に相続させることが考えられます。
それによって、受け継ぐ子どもがいないため別の家系に先祖の大事な不動産が移ってしまいます。
この場合、被相続人の家系からすると不都合でありますが、配偶者からすると住んでいた住居を追い出されては困りますよね。
この配偶者居住権の創設により、配偶者には亡くなるまでの居住権が保証され、不動産などの財産は被相続人の家系にそのまま留めることができます。
また、年齢を重ねて再婚した場合、結婚した時点から配偶者に相続権が認められます。
そうなると、前妻の子どもは短期間の結婚で財産の半分を持っていかれるのを嫌がり、遺産分割で揉めてしまうことも考えられます。(それを原因に、入籍をあきらめる方もいらっしゃいました。)
しかし、被相続人からすると、死んだ後に大切な配偶者が、子どもたちから家を追い出されてしまうのも悲しいですよね。
これも、配偶者居住権の保証により、少し解決できるかもしれません。
この配偶者居住権は、婚姻期間が20年以上ある夫婦で、生前に配偶者が贈与をしている場合に適用されます。
内縁や同性婚には認められません。
ここで、現代の家族スタイルは様々で、夫婦のあり方も様々であることが考えられます。
日本の民法で定められた夫婦のみしか適用されないという点が、現段階で問題とされています。
平成30年7月6日に衆議院本会議で可決・成立しましたが、まだ公布日は確定していません。
できることなら、はやく施行されて欲しいですね。
この配偶者居住権により、居住権と所有権を分けることで、夫婦のどちらかがなくなっても、残された配偶者は亡くなるまで住居を保証してもらえます。
そして、相続人にとっても、先祖代々の大切な不動産を別の家系に移ることを阻止できます。
しかし、施行さが確定していませんし、婚姻期間が20年以上の夫婦にしか適用されません。
それまでの節税に効果的な不動産の相続について、ぜひ弊社にご相談ください。